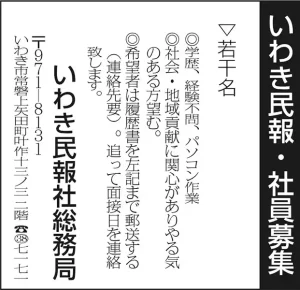<きょう15日は「終戦の日」。戦争を体験した一人の市民の声を紹介したい>
「空襲警報が鳴ると、『姿勢を低くし、耳をふさぎ口を開けるように』と言われました」。好間町の会川幸さん(89)は、つい昨日のことのように当時について振り返ってくれた。敵機から爆弾が落ちた際の衝撃によって、鼓膜が破れたり、目玉が飛び出さないようにするための教えだ。
現在の平字南町に生まれ、太平洋戦争が始まった1941(昭和16)年は、平市第三国民学校(現・平三小)の1年生。毎朝の登校時には必ず、天皇・皇后の御真影(写真)を安置する「奉安殿」にあいさつをした。「小さなお社が校舎わきにありました」と思い出す。
戦時下、ちょっとした幸運に恵まれたことが忘れられない。日本軍に物資をより多く回すため、衣類は配給制で、制服は1クラスに2着しか割り当てがなかったが、会川さんはクラスメイトとのじゃんけんに勝ち、そのうちの1着を手にすることができた。
■戦時色濃くなる街の風景
防空演習と呼ばれる隣組の訓練があった。赤い布切れに砂を詰め、焼夷弾に見立てて屋根に置く。その後は水槽からのバケツリレーで、火を消す真似をする。「いま思えば馬鹿馬鹿しいですが、みんな真剣にやっていました」
庭先に防空壕を作ることも当たり前だった。近所の芸妓が腰巻姿になって、背丈ほどの穴を掘り進め、その上に枝で形ばかりの屋根をこしらえていた。「庭のない家は、縁の下に掘っていましたね」。どこもかしこも戦時色が濃かった。
戦争によって街の風景は一変した。空襲に伴う延焼を防ぐため、平の中心市街地では、家屋を強制的に取り壊す「建物疎開」が行われた。「平駅(現・いわき駅)の周辺では建物に綱を付けて、そのまま引き倒す様子があちらこちらでありました」と、会川さんははっきりと覚えている。
上の姉が磐城高等女学校(現・磐城桜が丘高)に通い、神奈川・横須賀海軍工廠に勤労動員された。いとこが海軍の兵隊で、彼女たちがいることを知ると、戦艦から陸に向かって手を振ってくれた。しかし、ある日を境にその姿はなくなった。「誰言うともなく戦死したんだと感じた」と悲し気な表情を見せた。
■記事から透けて見える戦争の「におい」
終戦は義母の実家、福島市町庭坂で迎えた。父から「日本が負けた。戦争は終わった」と伝えられた。すると近くで地元の青年たちが、太鼓や鉦(かね)を手に踊りだした。騒ぎを聞きつけた軍国主義の男性が「戦争に負けたのに何事だ」と激怒していた。こうした無常さは、少女の心に深く刻まれた。
戦後は、平字六人町と三和町合戸で飲食店「鮎川」を経営し、広く市民に親しまれた。引退したいま、世の中が再び戦争の空気に包まれつつあると感じる。「私たちの生活は一見すると平和ですが、新聞の記事からは戦争の『におい』がします」と指摘する。
あの時代を経験し、「戦争は大変愚かなこと。どこかまたおかしくなっている」と打ち明ける。少しでも自分の話が役立つのならばと、温和ながら真剣な眼差しでそう訴えかけた。
ニュース
きょう終戦の日 好間町の89歳・会川さんに聞く 戦時下のいわき